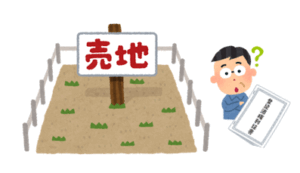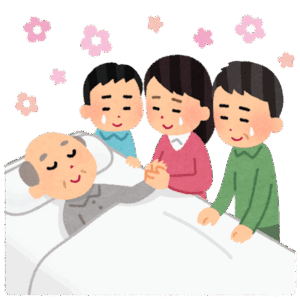こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。
さて、今回は、借地権の基礎知識についてご説明をいたします。
「土地は借りているだけなので、持っている不動産は家屋だけです」
多くの方が誤解をしていますが、借りた土地の上に自分の家を建築し、地主に地代を払っている場合、その方は、借地権という権利を所有していることになります。
借地権は、売却することもできれば、贈与することもでき、通常の所有権と同じように扱うことが可能です。それゆえに、借地権は相続税の対象にもなってきます。
「うちは家と預金だけだから相続税は心配ない」と考えている方でも、借地権の評価額をプラスすると、相続税の納税義務が発生することはよくあるケースです。
借地権の評価額の調べ方
借地権の評価額は、国税庁のホームページから誰でも調べることができます。「路線価」とキーワード検索すると、道路一本一本に値段(単位:1000円)が振られた日本地図(路線価図)が出てきます。そして、その値段の隣にアルファベットのA~Gまでがあり、これが借地権割合を示しています。「土地の面積×路線価×借地権割合」という算式で計算した価格が、(実際には地形などによって多少増減することがありますが)借地権の評価額となります。
一般的な住宅街では、借地権割合が60~70%に指定されていることが多いため、地価の高い地域では、借地権だけでも何千万円という評価額になることがあります。相続税の計算に非常に大きな影響がありますので、十分に注意しましょう。
地主に土地を返却する際、「借りたものはタダで返すのが当たり前」と思っている方が多いのですが、違います。借地権は地主に対してであっても、売却できます。まわりの方が無償で返しているからといって、あなたまで無償で返す必要はありません。ここでは、借地権の基礎知識についてご紹介します。
借地権の2要件
まず、借りた土地のすべてに借地権が発生するわけではありません。借地権という権利は、①借りた土地の上に建物を建築すること、②地主に対して地代を払うこと、この2つを満たしたときに発生します。
もともと戦時中の、法律が整備されていない時代では、地主の権利が非常に強く、借地人(土地を借りている人のこと)は地主からの無理な要求に従わなければ土地を追い出されていました。
そこで、1941年に借地人の権利を守るための法改正が行われ、正当な理由(地代の渋滞等)がない限り、地主は借地人を追い出すことができなくなりました。
最大のポイントは、たとえ借地契約の期間が満了したとしても、借地人が「まだここに住み続けたいから地代を払い続けます」と意思表示した場合、地主が「土地を返してほしい」と言ったとしても、借地人契約は自動更新されるのです。
地主と借地人の攻防戦
借地権という権利は、地代を払い続けさえすれば、地主都合で追い出すことはできないという、非常に強い権利となったのです。しかし、今度は借地人の権利が強くなりすぎたため、「一度、土地を貸したら永久に土地が返ってこないじゃないか!金輪際、新しく土地を貸し出すのはやめよう」と、土地を貸すことに否定的になる地主が多くなってしまいました。そこで、平成4年に法改正を行い、新たに定期借地権という「契約期間が終了したら必ず地主に土地を返還するという新しいタイプの借地権を誕生させました。平成4年8月以降に新たに借地契約をする場合は、通常の借地権と、定期借地権を選択することができるので、かなり柔軟な法制度になったといえます。いずれにしても、ただの物の貸し借りとは異なり、土地の貸し借りには、借地権という権利が生ずるため、注意が必要です。
借地権のポイントを徹底解説!
まず1つ目のポイント「借りた土地の上に建物を建築すること」についてご説明します。建物とは、壁や天井などがあり、雨風をしのげるようなものをいいます(ビニールハウスがこれにあたるか争った過去の裁判では基礎や骨組みが強固なものであれば、建物と認めるという判決が出ました)。
2つ目のポイント「地主に対して地代を払うこと」は重要です。「親の土地の上に子供が家を建築し、親に対して地代を払わない」というケースはよくあります。この形を法律用語で使用貸借(しようたいしゃく)といいます。使用貸借の場合、当然、借地権は発生しませんので、借地借家法の保護は受けられません。親と子が喧嘩になり、「今すぐ、家を取り壊して土地を明け渡せ」と言われれば、子はそれに従わないといけないのです。
また、「地代を払えばいいのなら、1円でもいい?」と疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれませんが、さすがに1円だと使用貸借とみなされる可能性が高いでしょう、一般的な地代(年額)の相場は、その土地にかかる固定資産税・都市計画税の2倍~4倍と言われています。
借地人が死亡した場合
借地権を相続する際は、誰が借地権を相続するかを遺産分割協議書で決めるか、あらかじめ遺言書で指定しておく必要があります。相続する人が決まったら、その旨を地主に伝え、覚書を作成するか、借地契約書の更新をしておきましょう。
なお、借地権の相続には、承諾料や更新料は不要とされています。注意したい点として、相続が発生してから、相続する人が決まるまでの間の期間も、地代は地主に払い続ける必要があります。相続する人が決まらないからという理由であっても、地代を滞納すれば、地主から立ち退きを言い渡されるかもしれません。
地主が死亡した場合
地代を銀行振込で受け取っていた場合、その銀行が凍結されると、入金を受けることもできなくなり、借地人が慌ててしまいます。銀行を凍結するのであれば、速やかに別の口座情報を伝えるか、落ち着くまでは現金で地代を受け取るのも1つの手です。
昔からの慣習で、地代のやり取りを現金で行っている方も多いのですが、できれば銀行振込で行うべきです。理由は、現金のやり取りを続けていると、地代の滞納等があったときに、「払った・払ってない」の水掛け論に陥る可能性があるからです。きちんと記録を残しておくのが紛争防止には効果的です。
地主から立退料をもらおう
「借りたものはタダで返すのが当たり前でしょ?」と思っている方が非常に多いです。一見、当たり前のように感じるとは思いますが、こと、借地権が生じている土地の貸し借りにおいては、地主に借地権を買い取ってもらいましょう。
そもそもですが、借地権は、地主の承諾があれば、第三者に売却することも可能です(その際、売買代金の約1割を承諾料として払う必要があります)。また、借地権を相続する際は、他の財産と同様に、借地権も相続税の対象として計算されます。このように、借地権は、ただの借りている権利ではなく、売ることもでき、相続税もかかる、所有権に非常に近い権利なのです。この権利が借地人に帰属している以上、これをタダで地主にプレゼントする必要はありません。
地主が高圧的な態度を取ってきたときの対処法
ただ、地主と借地人のこれまでの関係性から、「これまで土地を返すときに、お金を要求した人なんていないよ?」と高圧的に言われ、タダで借地権をお返ししている方が多いのが実態です。
この点について、もし借地契約書に「借地権を返還するときは、無償で返還する」という文言があったとしても、借地借家法第9条「この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。」という規定により、無効とすることができる可能性があるので、弁護士に相談してみましょう。
地主の立場としても、将来発生する多額の相続税を払うために、金融資産は少しでも多く残しておきたいと思うでしょう。お互いが納得する着地点を、しっかり模索していきたいところですね。
今回は、知っているようでよく知らない、借地権の基礎知識について、まとめてみました。
今回の記事を参考にしていただいて、相続の為の手続に取り掛かる方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、お時間等が無く、自分で手続きを実施することが難しい場合や、相続した不動産の売却処分(換価分割)でお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。
なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。