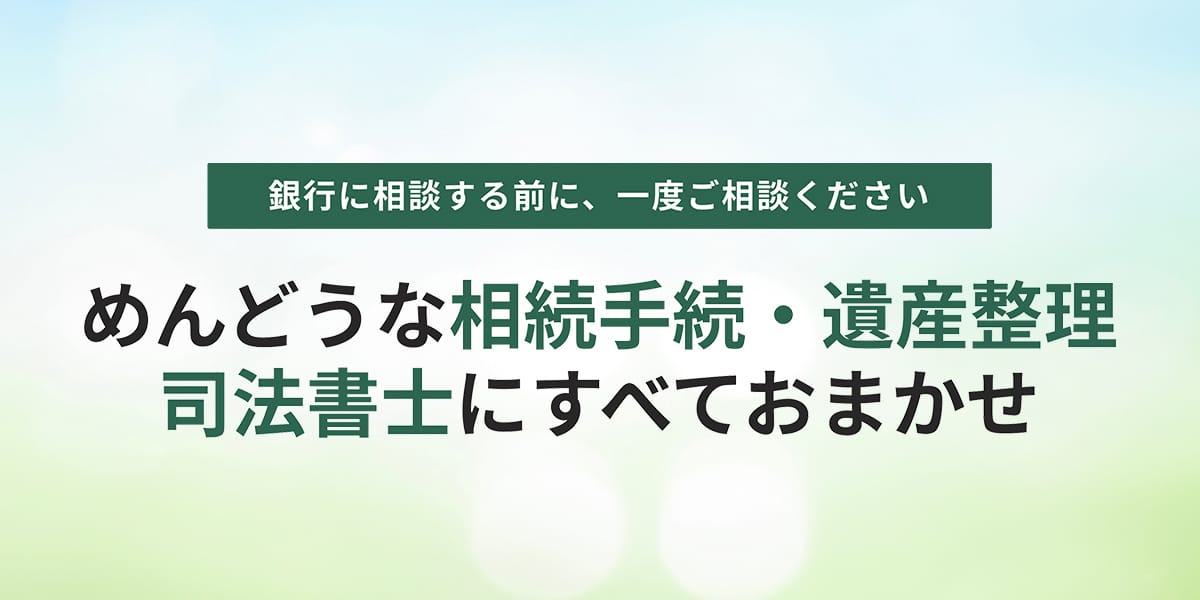銀行に相談する前に、一度ご相談ください
将来のトラブルを防ぐため
遺言書作成は司法書士にお任せください
将来の家族の争いを防ぎ、あなたの想いを確実に残すために
公正証書遺言の実績豊富な司法書士が
遺言書作成から相続手続まで責任を持って行います
受付時間:平日9:00〜18:00
遺言書作成支援サービス
安心して相続を行うために司法書士が遺言書の作成を一括でサポートします
こんなお悩みありませんか?
- 子どもたちが遺産で揉めるのではないかと心配や不安がある。
- 配偶者に全財産を残したいが、どうすればいいか分からない
- 前妻との子どもがいて、相続が複雑になりそう
- 自分が亡くなった後、家族が困らないようにしたい
- 遺言書の書き方が分からず、後回しにしている
- 銀行に相談したが、費用が高額で驚いた
遺言書は「縁起でもない」と先延ばしにしがちですが、
実は、遺言書がないことで起こるトラブルが年々増加しています。
遺言書の作成件数も急増しています
公正証書遺言の作成件数
平成元年:4万935件
令和6年:12万8,378件
34年間で約3倍に増加
自筆証書遺言の検認件数
昭和60年:3,301件
令和5年:22,314件
36年間で約6倍に増加
なぜ遺言書の作成件数が増えているのか
2025年からは団塊の世代の方々が後期高齢期を迎え、相続の発生を見越した終活をし始めていることが大きな要因と考えられます。
また、もともとそれぞれのご家庭で「遺産の分け方で子供たちに揉めてほしくない」という、残される家族への配慮があったことは、言うまでもありません。
高齢者の割合が増えて高齢者社会化したからというだけでなく、相続のトラブル自体が増えてきたことも大きな要因です。
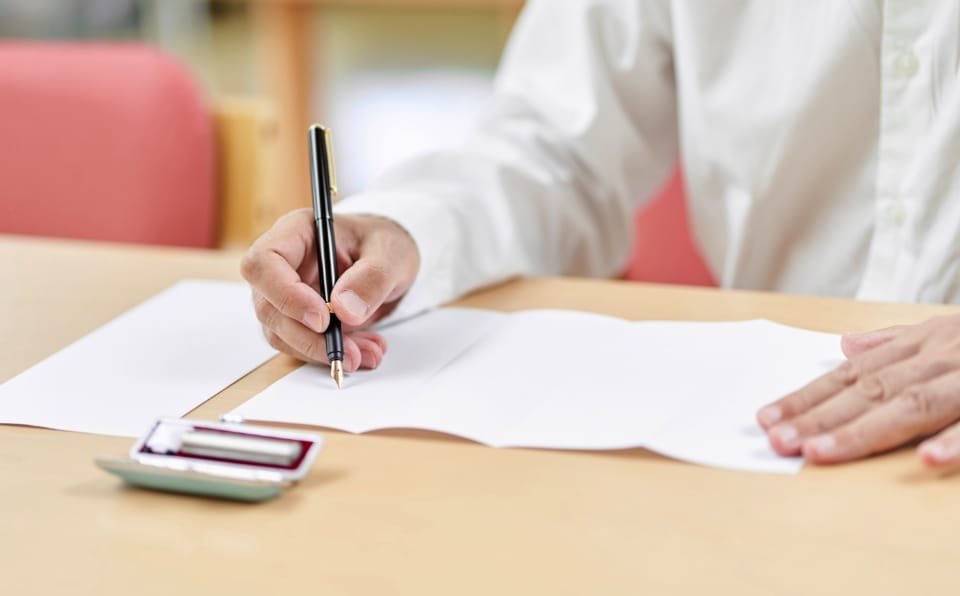
- 戦後の新民法概念が周知され、兄弟間の遺産分割について平等意識が定着していること。
- 現役世代である相続人たちは、異常に長引く賃金停滞に加えて物価高と不況も重なっている。
その結果、子どもの教育費や住宅ローンで苦労しているご家庭が急激に増えていること。
上記の要因により、家族の相続発生後の権利を個人として強く主張する相続人の方が増えている傾向にあります。
遺言が必要な7つのケース
1子どもがいない夫婦
配偶者が亡くなると、直系の親や兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が住み慣れた家を相続するために代償金を支払わねばならない場合があります。
また、被相続人の兄弟姉妹が高齢の為、既に死亡している場合も多く、甥姪まで相続権が拡大していることがあります。ご存命であっても、認知症が発生していて遺産分割協議自体が不可能になるケースが非常に多いです。
ご夫婦がお互いにあらかじめ遺言書を準備しておく必要があります。
2前妻との間に子どもがいる場合
前妻の方とのご離婚時の状況にもよりますが、前妻の子と後妻の間で相続を巡ってトラブルが発生するケースが非常に多いです。
遺言で明確に分割の方針を示すことが大切です。
3別居中の配偶者がいる場合
別居状態であっても、戸籍上離婚が成立していないのであれば、法的には配偶者(夫または妻)のままです。その為、相続権が発生します。
相続財産をご子息やご息女にのみ残したいと望まれる場合、ご自身の子と別居配偶者の関係が良好でないのであれば、遺言を作成する必要があります。
4内縁の配偶者がいる場合
内縁関係の配偶者には相続権がありません。
財産を内縁の配偶者に確実に残すためには、遺言の作成が必須です。
この点について、離婚の際の財産分与と混同して、遺言書を全く残しておられない方が多数おられます。
5家族以外の第三者に財産を残したい場合
息子(娘)の配偶者に財産を残したい場合や、仕事仲間・お世話になった友人に財産を残したい場合です。
法定相続人以外の第三者には相続権がないため、財産を譲りたい場合は、「遺贈」という名目で遺言書を作成して意思を残しておく必要があります。
また、法定相続人がいない場合であっても、家庭裁判所で相続財産清算人が選任され、財産の処分方法が検討されますが、申立ての準備には非常に手間と時間がかかります。
遺言で希望する財産の譲渡先をあらかじめ明記しておくことで、確実に意思を反映できます。
6行方不明の相続人がいる場合
ご子息やご息女の内、既に音信不通になった方がいる場合や、事故などで生死不明・行方不明の方がいる場合、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てが必要です。
この場居も、時間と費用が非常にかかるため、遺言で遺産分割協議の難航を回避するようお勧めします。
7家業を特定の相続人に継がせたい場合
息子(娘)の配偶者に財産を残したい場合や、仕事仲間・お世話になった友人に財産を残したい場合です。
法定相続人以外の第三者には相続権がないため、財産を譲りたい場合は、「遺贈」という名目で遺言書を作成して意思を残しておく必要があります。
また、法定相続人がいない場合であっても、家庭裁判所で相続財産清算人が選任され、財産の処分方法が検討されますが、申立ての準備には非常に手間と時間がかかります。
遺言で希望する財産の譲渡先をあらかじめ明記しておくことで、確実に意思を反映できます。
将来のトラブルを防ぐため遺言書作成は司法書士にお任せください
安心して相続を行うために司法書士が遺言書の作成を一括でサポートします。
家族信託・民事信託のご相談も受け付けております。家族信託・民事信託はこちら
受付時間:平日9:00〜18:00
遺言作成のルールと種類
遺言書はいくつかの種類に分かれ、法律でその形式が定められています。
自筆証書遺言
遺言者本人が内容部分を始め、全て自筆で作成する。
公正証書遺言
本文を公証人が作成し、公証役場で口述して内容を確認、保管も行う。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にして作成、封印は公証役場で実施する。
基本的には、公正証書遺言の方法にて、司法書士や弁護士を遺言執行者に指定するやり方が、最も堅実です。
公正証書遺言のメリット
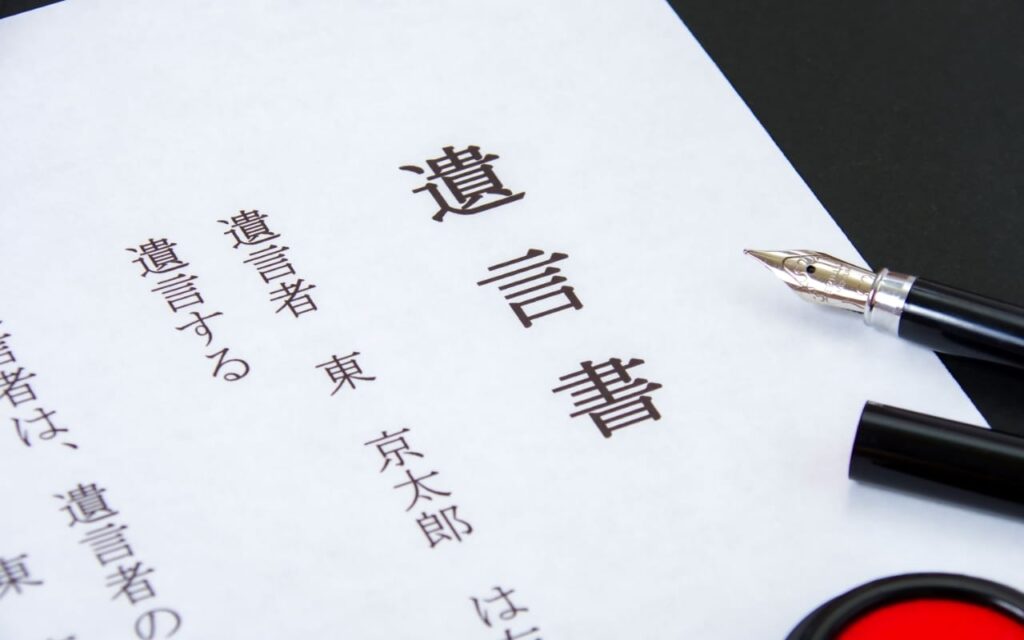
メリット1
手書きが不要
自筆証書遺言と異なり、内容を確認する必要はあるものの、公正証書遺言は全文を自書する必要がありません。
また、遺言者本人に、書面で書く力がなくなった場合も作成可能です。
メリット2
法的に確実な内容と保管
公正証書遺言は、公証人が証人2名と共に、客観的な立場で内容を確認し、無効のリスクが低いです。
また、遺言内容原本も電子化されたデータで公証役場内で保管されるため、親族や利害関係による破棄や変造、紛失の恐れもありません。


メリット3
ご遺族の手間を軽減ができる
家庭裁判所での検認手続きが不要のため、ご相続発生後の、ご遺族の負担が軽減されます。
「公正証書遺言は、検認手続きが不要なので、他の相続人に遺言内容を知られず、内密に相続財産を取得できます。」という説明を、専門家がすることがありますが、これは明らかな間違いです。
公正証書遺言であっても、遺言があることを全相続人に通知する必要があります。
そして、この通知を怠ったときには、遺言書隠匿に該当し、相続欠格(相続する権利を失うこと)になることもあります(民法891⑤)。
引用
民法第891条⑤:次に掲げる者は、相続人となることができない。
①~④省略
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言作成の決定
遺言の内容や、対象財産について、基本的な方針を決めてください。
- 内容や方針は、必ずご本人様に決めていただく必要があります。
ご相談時、完成までの間に、周辺知識や事例のご提案をさせていただきます。
公正証書遺言作成のご相談
はがくれ司法書士事務所にご相談ください。
ご希望を伺いながら、最適な方法をご提案します。
遺言者との面談
早い段階に遺言者とご面談させていただきます。
どの程度複雑な内容で、財産の種類、相続人の数、を加味して、遺言書案を作成するためです。
- ご本人様の認知能力に、もしも不安があれば、別途、医師の診断をお願いする場合がございます。
遺言書案の作成
司法書士が遺言書案を作成し、ご本人様に、内容を確認いただきます。
公証役場での作成
公証役場で遺言を作成します。
- 状況に応じて公証人にご自宅や施設に出向いてもらうことも可能です(別途費用が発生します。
通常、最初のご相談から、概ね1か月~2か月程度で完了しますが、公証役場の予約状況により異なります。
遺言書作成の料金
個別具体的な金額は、ご相談お打ち合わせの後に、事例や内容に応じて個別に算定させていただきます。
| 業務の種類 | 司法書士の報酬・手数料 | 実費 |
|---|---|---|
| 遺言公正証書原案作成 | 132,000円(税込)~/通 ※1 | 公証人費用 |
| 遺言立会証人日当 ※2 | 11,000円(税込)×2名 | 公証役場への交通費 |
| 遺言執行引受予諾契約締結 | 55,000円(税込)~ | |
| 遺言書保管 | 6,600円(税込)/年 | |
| 遺言変更手数料 | 55,000円(税込)~/回 |
※1 次の場合には、表の通り料金を加算します。
| 加算の要素 | 司法書士の報酬・手数料 |
|---|---|
| 遺産総額(負債含まず)が5000万円を超える場合 | 5000万円を超えるごとに33,000円(税込)を加算 |
| 不動産で筆数が多い 銀行口座数が多い 証券口座数が多い | 自宅以外の不動産などが存在する場合、物件が他管轄に渡る場合、次の加算をお願いします。 5,000円/筆・口座 |
| 内容が複雑・非定型 | 55,000~110,000円(税込)を加算 |
※2 遺言公正証書の作成には、証人2名の立会いが必要です。お客様が要件を備えた証人が用意できないときに、当事務所スタッフが証人を務めさせていただきます。
将来のトラブルを防ぐため遺言書作成は司法書士にお任せください
安心して相続を行うために司法書士が遺言書の作成を一括でサポートします。
家族信託・民事信託のご相談も受け付けております。家族信託・民事信託はこちら
受付時間:平日9:00〜18:00
よくある質問
- 銀行に遺言作成を依頼しないほうがいいですか?
-
銀行に依頼はおすすめできません。
- 銀行の遺言信託に携わる銀行員は専門家ではないので、間違いが多い。
必要な条項が抜けていたり、個別の最適化がされていない遺言書が多くあります。 - 銀行が遺言に取り組むのは遺言する方の資産把握が目的なため。
銀行は資産把握が主たる目的なので、遺言者や家族のことを考えつくした遺言書にはなりにくいです。 - 遺言執行者の報酬がかなり高額。
司法書士に依頼するよりもかなり割高になるケースが多いです。さらにそこから税理士報酬・司法書士報酬は別途必要となりますのでご注意ください。
- 銀行の遺言信託に携わる銀行員は専門家ではないので、間違いが多い。
- 遺言作成は結局どこに依頼するのがいいですか?
-
遺言を作成する段階ではあまり違いはありませんが、遺言の効力発生後、次のような違いが発生します。遺言作成を決意なさったら、相続のときを見据えて当事務所にお任せください。
デメリット 当事務所に依頼した場合 信託銀行 手数料が高額。
銀行預金の名義変更でも預金額の数%を取られます。専門家費用も別途必要です。信託銀行でないと出来ない業務はありません。銀行預金の名義変更は、定額となります。 税理士 相続税が発生しなければ、別の専門家を探す必要があります。
※ 相続税を扱わない・扱ったことのない税理士もおりますので、ご注意下さい。相続税が発生しなければ、当事務所で全て対応可能です。
相続税が発生しても、相続税専門の税理士を紹介できます。弁護士 トラブルが発生していなくても、遺産総額に応じた報酬請求されることもあります。
※ 相続紛争を扱わない・扱ったことのない弁護士もおりますので、ご注意下さい。遺産分割調停申立書作成なども安心の定額です。トラブルにならない方法もお伝えできます。
もしトラブルになってしまっても、遺産分割調停申立書作成・期日同行を通じ、あなたを徹底的に支援します。また相続紛争が得意な弁護士も紹介できます。行政書士 行政書士は登記をすることができません。相続登記は、司法書士を探す必要あり。行政書士でないと出来ない業務はありません。 当事務所にご依頼いただいた場合、行政書士への依頼は不要です。 他司法書士 相続登記のみ。
預貯金の名義変更手続はご自身でする必要があります。
紛争に発展したときは、弁護士を探す必要があります。当事務所では、預貯金の名義変更、遺産分割調停申立書作成・期日同行支援などを通じて、徹底的に支援します。 - 公正証書遺言さえ書いておけば、万全ですか?
-
万全とは言えません。
ひとつには、遺言で一気に財産を移してしまうと、相続人に多額の相続税がかかることがありえます。当事務所では、税理士と強い提携関係のもと、相続税をなるべく節約できるような方法をも提案いたします。後日別の遺言を書かれた場合には、後日の遺言内容が優先されます。相続人の中には、お客様を管理下におき、自分の都合の良いように遺言を書き直させる者もおります。それを予防する方法もご提案が可能です。 - 公正証書遺言を無効とする判決があるようですが?
-
残念ながら、本当です。
もっとも、無効とされた事例は、もともと遺言をする能力が無かったにも関わらず遺言を無理やり作らせたものや、公正証書遺言の方式に違反していたものです。
当事務所では、遺言の有効性が後日争いにならないよう、また、争いになった場合にも無効とならないよう、これら裁判例を徹底的に分析しておりますのでご安心いただけます。 - 兄弟姉妹に私の財産が行かないようにしたいのですが、可能ですか?
-
可能です。
ご兄弟は、法定相続人ですが遺留分を有していませんので、遺言でそのご兄弟以外に遺す旨を明記することにより、ご兄弟には行きません。 - 遺言書では遺言執行者を指定しておいた方が良いですか?
-
信頼のできる方を遺言執行者に指定しておけば、遺言執行者の就任後、相続人が勝手に(あなたの遺志を無視して)遺産分割協議することを防げます。確実に遺言を執行するには、遺言執行者を指定しておくことが必須です。
- 遺言執行者には、誰になって貰えば良いですか?
-
遺言執行者は、他の相続人から様々な主張(遺留分減殺請求、遺言無効主張など)を受けて、判断をしながら、遺言執行する必要があります。遺言執行に失敗した結果、損害賠償請求を受けることもあります。
また、中立でない場合には、感情的な対立を招くこともあります。
さらに、相続人中の一人を選任すると、遺言を隠されてしまう可能性があります。
よって、あなたの遺言を確実に実現するためには、遺言執行者には相続人とは利害関係にない司法書士を指定されるようオススメします。
将来のトラブルを防ぐため遺言書作成は司法書士にお任せください
安心して相続を行うために司法書士が遺言書の作成を一括でサポートします。
家族信託・民事信託のご相談も受け付けております。家族信託・民事信託はこちら
受付時間:平日9:00〜18:00